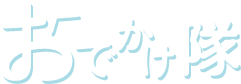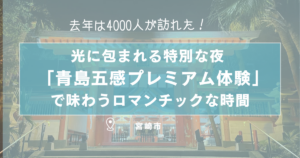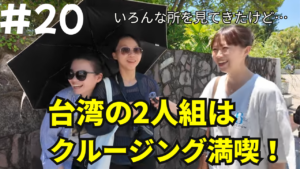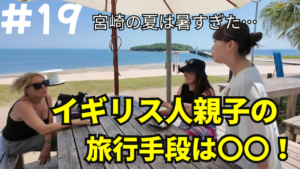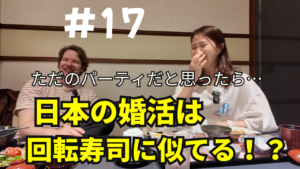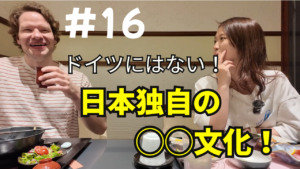こんにちは、かねちん夫婦です。
前回に引き続き、ドイツ人のトーマスさんにお話を聞いていきます。
東京に住んだことのあるトーマスさんならではの苦労話を皮切りに色々なエピソードを聞くことができました。
海外と日本の運転事情の違いや、食事の挨拶の考え方など沢山の魅力的な話題が詰まっています。

日本の運転事情は、海外目線から見てどうなのか気になりますよね!
宮崎は遊び心がある!


トーマスさんは、宮崎を東京よりもずっと遊び心のある場所だと感じているそうです。



宮崎は何もないけど…
もちろん東京には宮崎に比べてたくさん遊べる場所やイベントがあります。
それに対して宮崎はストレスが少ないと話します。



何もすることがありません。
宮崎では自分でやることを見つけなければならないと語ります。
東京に住んでいたときは、自分でみつけるというよりも、情報が手の中に落ちてくる感覚だったそう。
東京では、毎日東京のイベントをWebサイトの一覧で確認していました。



お祭りを見つけたり、何かを見つけたりする事は簡単だった。
宮崎での生活は、東京での生活のように、毎日やることを見つけることは少し大変だと話します。
しかし東京という街に、トーマスさんは多くのエネルギーを奪われていたそう。
東京時代の通勤ラッシュ
東京にいた頃は、通勤で電車に乗っていました。
新宿で電車を乗り換えなければならずとても大変だったそう。



これは毎日本当にイライラしました。
新宿駅の朝の乗り換えは非常に大変です。
新宿駅にはJR、小田急、京王、東京メトロ、都営地下鉄と多くの路線が乗り入れ、膨大な乗り換え客が集中します。
複雑な駅構造も混雑に拍車をかける形になっています。
世界一の乗降客数を誇る新宿駅が、朝の時間帯は通勤・通学客でごった返しているんです。
ラッシュアワーにその混雑を避けたくても避けられないのが東京の現状。
東京で車を持っていても、それほど良くはないとトーマスさんは話します。



なぜなら、とても高いからです。



たしかにね…
東京で車を持つと、駐車場代が月数万円と高額な上、ガソリン代や保険料もかさみます。
さらに、2年に一度の車検費用や自動車税も必要に。
そして東京周辺の道路は常に渋滞しているため、目的の時間に到着しないリスクも地方に比べて高くなります。
東京は地方に比べて公共交通機関が発達しているので、維持費を考えると「もったいない」と感じる方が多いかもしれませんね。
日本と海外の運転事情


通勤ラッシュの話から運転事情に話は移ります。
日本のドライバーは一般的にとても運転が上手いと思います。



何と比べてですか?



世界のほとんどと比べてだと思います。



日本の運転免許は難しいよ。
日本の運転免許は、海外に比べて取得が難しいと言われることが多いんです。
なぜ難しいのかというと、多くの国では個人的な練習で試験を受けられるのに対し、日本では指定自動車教習所に通い、決められた時間数の学科教習と技能教習を受けるのが一般的です。
さらに、S字やクランク、車庫入れといった技能試験の採点基準がとても細かく、ちょっとしたミスでも減点対象になってしまいます。
学科試験もひっかけ問題が多く、90点以上が合格ラインと高めなことも特徴の一つ。
しかしこのような厳しい制度があるからこそ、日本の交通安全は高い水準を保てているとも言えますよね。
日本はクラクションを鳴らさない!
トーマスさんが日本で運転を始めてから驚いていることがあります。



誰かがクラクションを鳴らすのを聞いたことがありません。
確かに日本ではあまりクラクションを鳴らす場面を見かけませんよね。
トーマスさんの故郷ドイツ、特にベルリンの運転を次のように話します。



ベルリンのドライバーはもっと攻撃的です。
もし一度でもミスをしたり、青信号を待っていて、少し長く待ちすぎたりしていると、すぐにクラクションを鳴らしたり降りてくることもあるんだとか。
国が違うと、運転の仕方にも違いが出てくるのですね!
食事の挨拶


2人の前に食事が運ばれてきました。
ここで2人は食事の時の挨拶に移ります。
ドイツの挨拶は?



いただきます。



(日本に来て)いまだにいただきます、って言ってないよ。



ドイツでは食事の挨拶はどんなもの?



ドイツでの食事の挨拶は「Guten Appetit!(グーテンアペティート)」と言います。
これは「良い食欲を!」という意味で、食事を始める人に対して使われる、日本でいう「いただきます」に近い表現です。
この挨拶には、食事が美味しく、楽しい時間になるようにという願いが込められています。
しかしトーマスさんは、成長するにつれてその言葉を使わなくなりました。
お父さんが長い間料理人として働いていて、とても働き者だったそうです。
そんなトーマスさんのお父さんは、形式はあまり気にしない人でした。
そのため家では食事の挨拶を言う必要はなかったそうです。



幼稚園でお昼ご飯を食べるときは、言わなければなりませんでした。
形にとらわれなくても、食事への感謝の気持ちはきっとつねに持ち合わせているのでしょう♪
宮崎はストレスが少ない!





宮崎はずっとストレスが少ないよ。
宮崎は以前住んでいた東京にくらべ人が少なく、車があればどこにでも行けると語ります。
ストレスは無いけど車が必須!?



宮崎では車が必要ですね。



そうだね。
宮崎は広い為基本的に車が第一の移動手段となります。
トーマスさんの学生の中には、車を持っていない人もいます。



彼らがどうしているのか…



私もです。



どうしてるの?徒歩?



バイクを持っているよ!
トーマスさんはバイクでの生活に興味を示します。



どうやって?食料品を買いに行けるの?



うん、いけるよ。



どこに荷物を入れますか?



バッグの中にいれちゃう。



なるほど…
さほちゃんは実家暮らしなので、自分で食料品を買う必要はないと話します。
一人暮らしをしたことは…





今おいくつですか?



22歳です。
さほちゃんは以前一人暮らしをしていたと話します。
ワーキングホリデーでトロントに行くことに決めてから、宮崎で2年間ひとり暮らしをしました。



初めての一人暮らしでしたか?



ええ、トロントの前に。



その後トロントで1年間、そして両親の元に戻ったんですね。なぜですか?
トーマスさんは少し不思議そうにさほちゃんに訪ねます。
日本の賃貸事情は難しい





ひとり暮らしに戻ろうと思っていたんだけどね。
さほちゃんがトロントから日本に帰ってきた時大学4年生で、就職するのに1年しかありませんでした。



基本的に、日本では最低2年間だから…



私も 同じ問題を抱えています。



だから部屋を見つけるのが本当に難しかったんだ。



日本では賃貸事情がむずかしいよね。
トーマスさんは、日本に来る前に住んでいた国とは賃貸方法が大きく異なると話します。



日本は非常に特殊なシステムです。



たしかにね。
日本の賃貸契約は、海外に比べ特殊です。
返還されない「礼金」や契約更新時の「更新料」、借主と同等の責任を負う「連帯保証人」制度は、実は日本ならではの慣習なんです。
海外では保証金(デポジット)のみが一般的で、保証人の代わりに個人の信用情報が重視されます。
こうした違いは外国人にとって高いハードルでしたが、近年は保証会社の利用も増え、借りやすい環境が整ってきています。



人々は会社を使って貸す傾向があります。



保証会社のことだね。
また家賃を支払う相手も、実際の所有者や家主に払う事はほとんどありません。
借り主と家主の間に仲介会社があり、借り主は仲介会社に支払い、そして仲介会社が家主に支払います。
この支払い方法も日本ならではなんです。
日本の責任の負い方も特殊


話を難しくしているだけのように見えるシステムですが、トーマスさんはメリットもあると話します。



日本の多くのことは、自分のリスクを最小限に抑えるよね。



責任を分散または共有する感じだね。
例えば会社で問題が起こった場合、責任を取るのは1人だけではありません。
部署全体の責任になったり、誰が間違いを犯したのか本当にわからないという状況も多々あります。



あなたはそれが良いと思いますか?



うーん・・・・
良いことも悪いこともあると答えてくれました。
でも、きっとこういったシステムは少なくとも今後20年は変わらないだろうと話します。



だからいいとか悪いとか関係ないかもね。
まとめ
前回に引き続きドイツ人のトーマスさんにお話を伺いました。
広い宮崎と大都会東京の違いについて、実際に住んだ意見を聞くことができました。
また、日本の運転は外国に比べて丁寧ということに驚きです。
そしてさほちゃんやトーマスさんだけでなく、日本の賃貸システムには困惑しているようですね。
▼インタビュー動画はこちら▼



ここまで読んで頂きありがとうございました♪